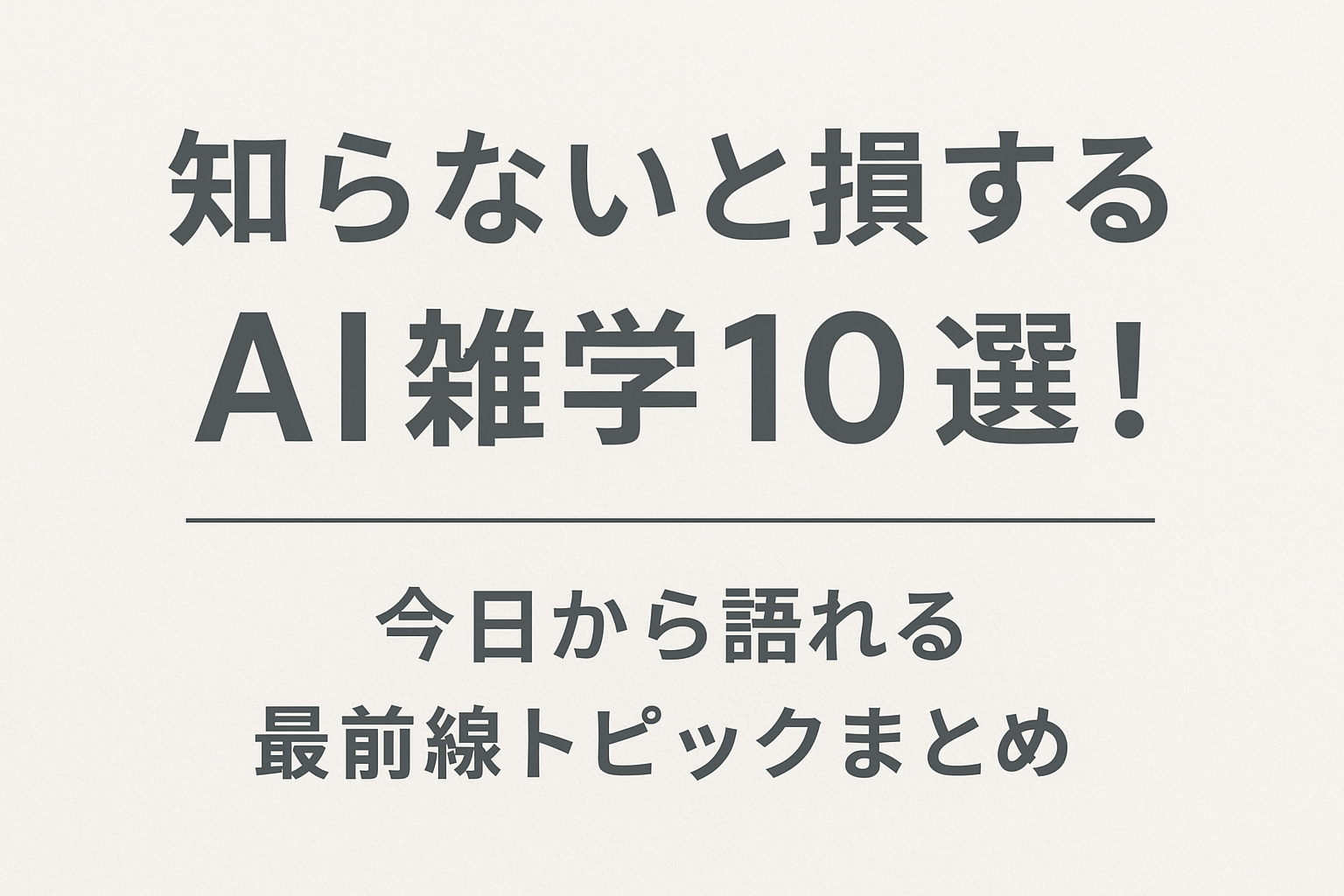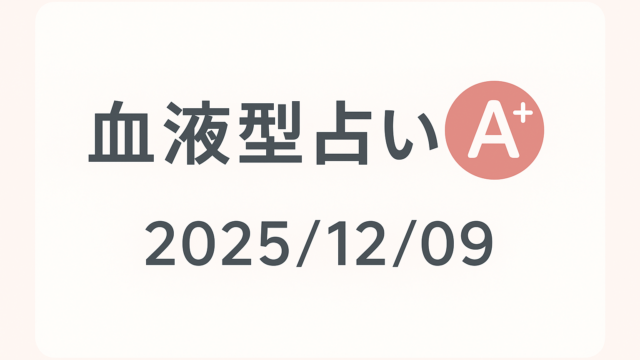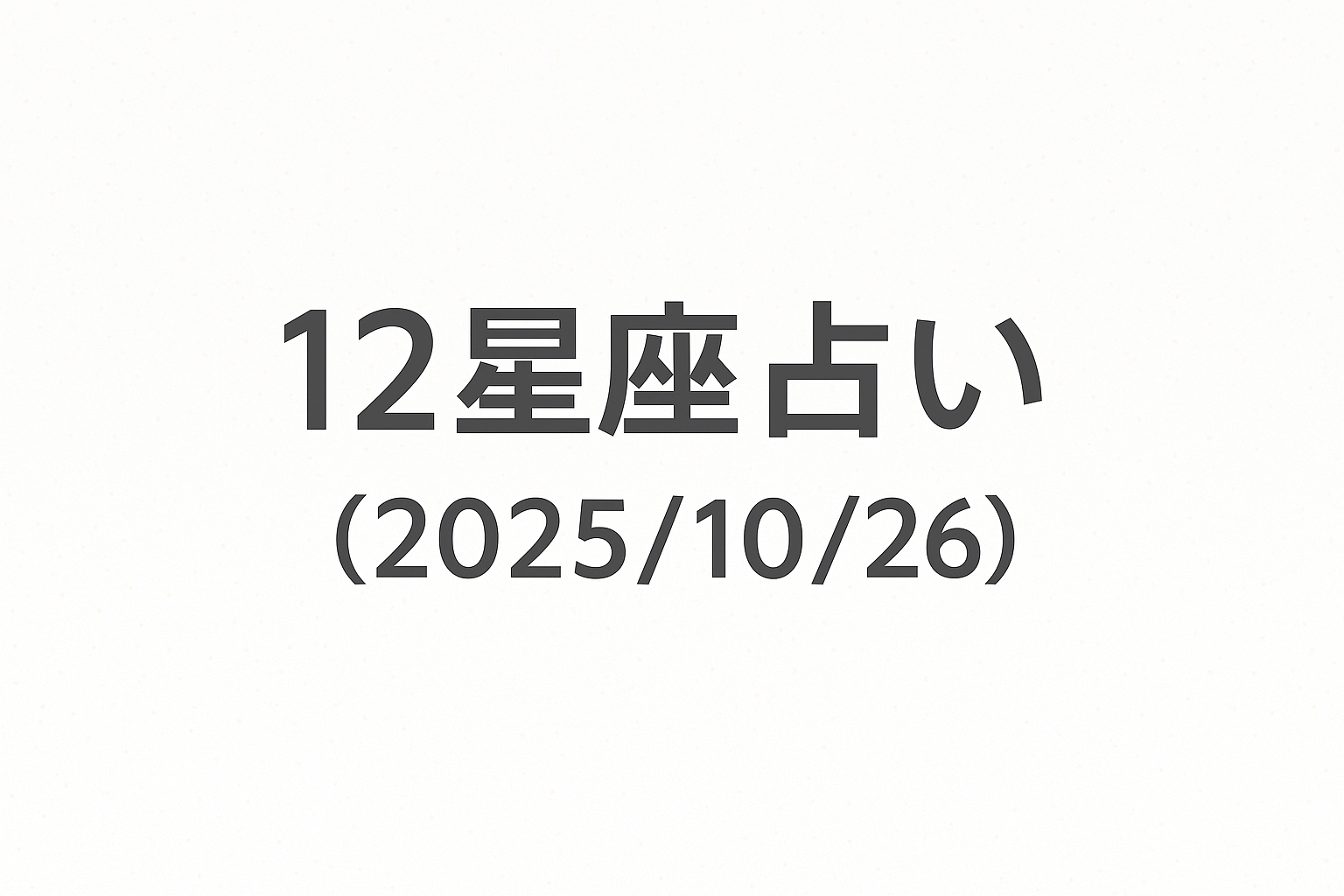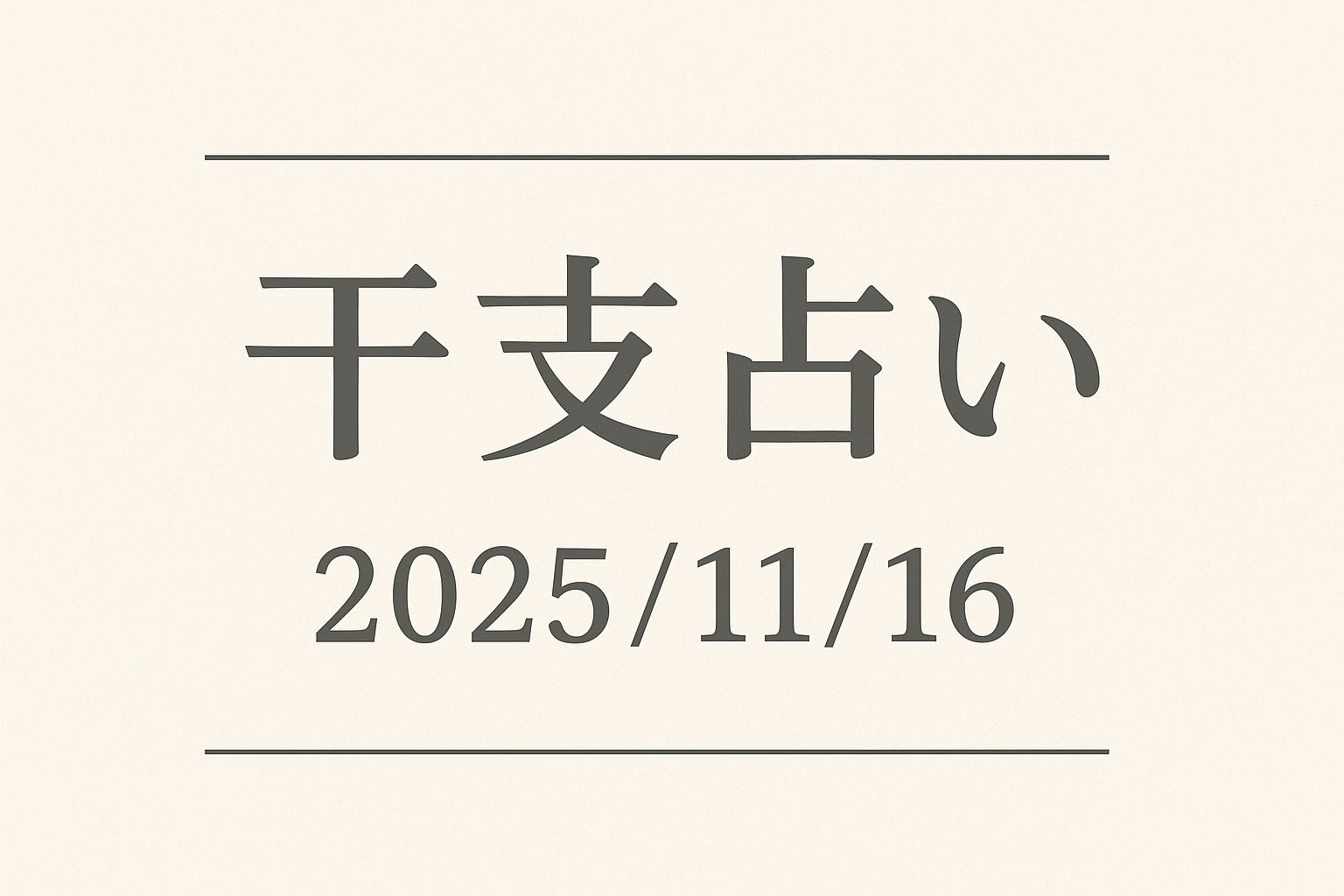AIの話題は日々刷新され、知らないだけで設計ミスやコスト増につながる“落とし穴”も増えています。ここでは、今日から語れて実務にも刺さる最前線の雑学を10個に凝縮。流行語ではなく、現場で効く長期トレンドに絞りました。
生成AIの進化と実務で効くトピック
- マルチモーダルLLMの標準化:画像・音声・表の入出力やツール呼び出しを一体化。長文コンテキストウィンドウとトークン圧縮により数百ページの資料も扱え、要約埋め込みで高速検索が可能に。
- RAG 2.0の定石:ベクトルデータベース+キーワードのハイブリッド検索、hyDE、再ランキング器、段階的要約を組み合わせて精度を底上げ。JSON SchemaによるStructured outputと関数呼び出し(Function Calling)でアプリ統合が安定します。
- プロンプト工学の実務:役割を明示するシステムプロンプト、スタイルガイド、few-shotの順序最適化、テンプレート化とプロンプトキャッシュでレイテンシ削減。現場の制約を織り込む“拡張現実的プロンプト設計”が再現性を上げます。
エージェントと自動化の今
- エージェントフレームワークの基本形:Planner-Executor、メモリ、Tool useを組み合わせ、関数呼び出しでAPI・DB・ブラウザ操作を統合。過剰自律はリスクなので、権限とスコープを細かくサンドボックス化。
- 評価・監視・ガードレール:ルーブリック自動評価とアンカー例で品質を常時モニタ。ハルシネーション抑制はCoT+検証用RAGの二段構え、機密情報はPIIマスキングとポリシーフィルタ、監査ログで追跡可能性を確保。
- ワークフロー実装の勘所:DAG/イベント駆動で分岐を明確化し、サーバーレス+キューでスケール。リトライとレート制御、ステート管理を整えると、業務システム連携でも落ちにくいパイプラインになります。
モデル最適化とコスト戦略
- 小型モデルを賢く使う:蒸留で知識を凝縮し、4/8bit量子化や混合専門家(MoE)でスループットを確保。推論最適化やGPU/CPUの適材適所で、クラウド費用を数十%削減できるケースも。
- 軽量微調整の実務:LoRA/QLoRAなどPEFTで少量データからドメイン適応。合成データでテストカバレッジを補完し、評価セットは厳密に分離。フェデレーテッドラーニングや差分プライバシーで機密を守りつつ改善可能。
リスク・規制・社会実装で押さえる点
- ガバナンスの必須知識:EU AI Actや国内指針を踏まえたAI監査、モデルカード、データリネージを整備。生成物の出自表示(C2PA)や透かし(水印)で信頼性を高め、AI TRiSM的な運用体制を構築。
- 著作権とライセンス実務:学習データのライセンス整合とオプトアウト手続、生成物の権利帰属、商用可否を明確化。オープンウェイトはApache-2.0/CC/Community Licenseなど条件差が大きく、コンプライアンス要件に直結します。
まとめ
“万能な一撃必殺モデル”は存在せず、RAG・エージェント・評価・最適化・ガバナンスを地道に積み上げるのが近道。今日の10項目を押さえれば、設計の勘所とリスク対応を同時に語れます。
CTA
関連ツール・おすすめ